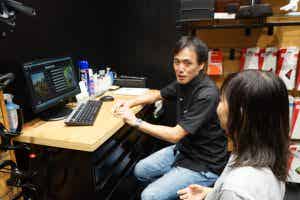ロードバイクのサイズを合わせる理由

ロードバイクは、自分の体格に合ったサイズを選ぶことが、とても大切です。自分にぴったりのロードバイクで疾走する瞬間は、気持ちいいものですよね。
「自分に合ったロードバイクを選ぼう!」と言うのは簡単ですが、選び方は難しいものです。スポーツ性が高いロードバイクは、少しのズレが痛みに変わることもあり、また乗るほどに筋肉がついてきたり、身体が柔軟になるとフォームが変わったりして、微妙に合わなくなります。
この記事では、
①自分のサイズに合うロードバイクの選び方
②それでも微妙に合わない場合、パーツでサイズを微調整する方法
の2つを紹介していきます!
ロードバイクの「サイズ」は、何の大きさが基準?

シティサイクルなどではタイヤサイズ(26インチなど)が、自転車選びの基準ですが、ロードバイクはどのモデルもタイヤサイズは、ほぼ一緒です。
フレームやハンドルなどは様々なサイズがありますが、ホイール(タイヤ)だけは基本的には700Cが多く、一部650B(700Cより小さめ)のロードバイクも存在しますが、モデル数も少ないのが現状です。
ホイールのサイズが700Cと決まっていると、自分の身体に合わせて選べるパーツは、フレームになります。ステムやシートポストでも、身体に合わせて調整はできますが、サイズ合わせの基本はフレームのサイズによって決まります。
走行性能/コスト/デザインの大部分も占めるフレームですが、さらに「サイズも合わせる」も考えて、選ぶ必要があります。
フレーム選びでは、自分が納得いくまで考えてみるのがいいでしょう。悩みながら考えるのも自転車趣味の楽しみの1つでもありますね。
そこで、サイズ選びのヒントになるのが、自転車メーカーが公表している「ジオメトリー表」です。
ジオメトリー表のここをチェックしよう
ジオメトリー表とは何でしょうか?
「自転車メーカーが公表しているフレームのサイズ一覧表」のことです。

例として、GIANTのジオメトリー表を見てみましょう。同じモデルでも、4つのサイズが展開されており、各チューブ長が記載されています。
フレームのサイズを選ぶ際には、このジオメトリー表を確認するのが良いでしょう。ただし、メーカーごとに表記方法が微妙に異なっており、メーカー別の比較ができません。
また身長ごとの標準的なサイズ数値はないので、適応身長の項目は参考程度に留めておくのがベターでしょう(アジアとヨーロッパでは、手足の長さなど体格が異なるためです)。身長が170cmでも、52サイズか54サイズか分からないような表記がされていることもしばしばあります。
ではジオメトリー表の、どの数字を重点的に見たらいいのでしょうか?
最低限抑えておくべき数字は、以下の3点です。試乗する際にはこの3つの数字を確認して、各ロードバイクを比べてみましょう。身長の数字だけでは分からない、手足の長さや柔軟性が現れてくる数字です。ここをチェックしながら試乗車に乗るのもおすすめです。
メーカーによって言葉の定義が微妙に異なるので、おおむねの定義です。
①リーチ長

リーチ長:BBからヘッドチューブまでの水平方向の距離
BB(ボトムブラケット)とはクランク回転軸を支える部分で、ダウンチューブ/シートチューブ/チェーンステーの3つのチューブの集合部でもあります。そのBBからヘッドチューブまでの水平方向の距離を、リーチ長と呼びます。
ハンドルまでの距離を合わせるために使う数字です。
②水平トップチューブ長

水平トップチューブ長:トップチューブからシートポストまでの水平方向の距離
この数字は、メーカー公表のジオメトリー表にも使われる「52サイズ」「54サイズ」と密接な関わりがあります。水平トップチューブ長が520mmなら52サイズ、540mmなら54サイズといった具合です。絶対的なイコール関係でもないので、「だいたいこれぐらいの大きさなんだな」と目安にする際に使う数字になります。
リーチ長と組み合わせて、サドルの位置を合わせるために使う数字です。
③スタックハイト

スタックハイト:BBからヘッドチューブ上端までの垂直方向の距離
エンデュランスモデル(長距離向き)とされる自転車は往々にして、このスタックハイトが高いことが特徴です。低めが好みの方はスタックハイトが高すぎないか必ずチェックしておきましょう(後述しますが、ハンドル高さをパーツで下げることは難しいためです)。
ハンドル高さを合わせるために使う数字です。
もし店舗や試乗会などで実際に乗ってみた際には、この3つの数字を確認しましょう。自分に合ったフレームサイズを、数字から考えて選びやすくなります。ただしこれだけで全てではないのが、フレームのサイズ選びの難しいところです。
迷うなら小さめのフレームサイズが、おすすめ

「自分の身長から考えると、52サイズでも54サイズでもどちらでもいいみたい…。どっちがいいのか分からない。」と迷うことがあります。迷ったときには小さいサイズを選ぶのがいいでしょう。
自転車パーツは、サイズを大きくするための調整はできるが、逆に小さく調整できないという構造的な制限があるためです。
試乗でベストサイズを見つけられればいいのですが、それ以外の場合には最終的に「小さめのフレームサイズ&パーツでサイズ調整」という方法になります。
また小さめのサイズのロードバイクには、メリットが多いためこの考え方がいいです。3つのメリットを紹介しましょう。
①サイズ調整が容易
小さなサイズのフレームを拡張するためのパーツが数多くあるためです。詳細は次の項目で紹介しますね。
②軽量化
フレームが小さい分、必要なフレーム素材も少なくなり、軽量化に繋がります。登り区間も多く走るロードバイクには、軽さも大事な要素になります。
③高い剛性
フレームが小さい分、変形量も小さくなります。フレームがたわみにくく、ガッチリした剛性を感じられるでしょう。ただし剛性が高すぎると、乗り心地が悪く感じる場合があるので要注意です。
サイズを調整するパーツもチェック!
「迷ったら、小さなフレームサイズ+各パーツで調整」と考えて間違いはないでしょう。
具体的にどの部分を、どのパーツで調整できるか見ていきます。この記事の2つ目の目的「フレームサイズが微妙に合わない場合、パーツで微調整する方法」の紹介です。
いまお持ちのロードバイクがあれば、調整方法の参考にもしてくださいね。
①ハンドル高さ
フレームのスタックハイト以外でも、ステム取付位置によってハンドル高さを決められます。

しかしハンドルを下げたい場合には、フレームの「ヘッドチューブ長」に制限されてしまいます。
ヘッドチューブ長が短いと、それ以下にハンドルを下げることが難しくなります。

ハンドル位置を高くしたくない場合には、スタックハイトが低いフレームを選ぶのがいいです。

どうしても下げたいのなら、角度が大きいステムやブラケットが下がった形のハンドルの導入などが解決策になるでしょう。
②ハンドル前後位置
基本的には、リーチ長に依存します。しかしそれ以上にハンドルの前後位置を調整したい場合には、ステムを交換しましょう。

ハンドルの前後位置は、ステム長で調整できます。ステムも安くはないので、手当たり次第に交換できませんが、自分のポジションを見ながら走っている際に「あと何mm遠くにしたい」など日常的に考えておくのがいいでしょう。
▼▼関連記事はこちら▼▼
③サドル前後位置
水平トップチューブ長とリーチ長の関係によって、サドルの前後位置は決まります。しかし、それ以外にも微調整ならパーツでも可能です。
やり方は2つ。1つはサドルの取り付け位置を変えてしまうこと。

サドルのレールには取り付け範囲があり、どこの位置で固定するかによって変えられます。レールの可動範囲がありますが、前後に10mmほど動かせるサドルが多いと思います。
「サドルの前後位置だけでは、自分のポジションに合わない」という方には、もう1つの方法です。シートポストの「オフセット量」を変更させることです。

フレームとサドルを繋ぐ「シートポスト」にも種類があり、サドル前後位置を決めることができます。ストレートの形のものから、後ろ乗り用にオフセット量が確保されたものまで様々です。
それ以外だと、サドルの形状によっても座る位置を変えられます。前乗り/後ろ乗りモデルや、ノズル長の違うものまで多種多様です。「サドル沼」と呼ばれるほど、自分の合うサドル探しは難しいものです。その反面、自分好みの座りやすいサドルを見つけられると、ものすごく嬉しいものです。
▼▼関連記事はこちら▼▼
④ハンドル形状

ハンドルを変えることでポジションは大きく変化させられます。ハンドル幅(C-C)/ドロップ量/リーチ長など、手を置くポジションを様々に変えられるのがハンドルの面白いところです。
他にもハンドル形状を変えたり、エアロポジションを取れるDHバーを取り付けたりと、フレキシブルにポジションを決められます。
▼▼関連記事はこちら▼▼
⑤クランク長

脚の長さと可動域に合わせて、クランク長を変えてみるのも、良い方法です。
足の動きが窮屈に感じるなら、クランク長を短くするもの手です。ただしクランク長の変化によって漕ぎやすくなるかは、個人差に左右されます。
ペダル/クリートの厚みによっても微妙にペダリングが変わるので、その場合はサドル高さで調整することをおすすめします。
フィッティングを受けてみる

自分で考えるだけではなく、プロの意見を聞くのが最も近道かもしれません。
フィッティングとは、「適切なサドルの高さ位置、ハンドルの位置など、自分の体の特性に合わせて、バイクを調整すること」を指します。プロのフィッティングコーチと、フィッティング専用マシンを使い、自分の体に最適なポジションを探すことができます。
以下の、記事も参考にしてください。
▼▼関連記事はこちら▼▼
最終的には実車で確認

いくら数字上で確認をしても、実際のフィーリングに勝るものなし。
店舗や試乗会に行き、実車のサイズ感を確認するのがベストです。またがってみて、ハンドルに手を置いてみて、走ってみる。これだけでもそれぞれのロードバイクの違いを実感できるはずです。自分にしっくりくるロードバイクは、どんな特徴があるか、ジオメトリー表と比較しながら考えてみてください。
また、プロの意見を生で聞くのもいいでしょう。店舗や試乗会のスタッフさんの知識や経験も、貴重な情報なのでどんどん取り入れてみましょう。
「自分が考えた、一番自分に合う、自分だけのロードバイク」を手にすることができれば、ロードバイク趣味がより充実したものになるでしょう。